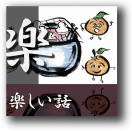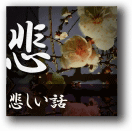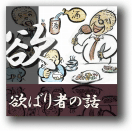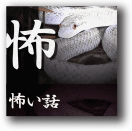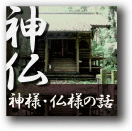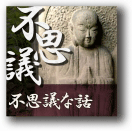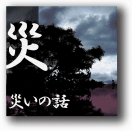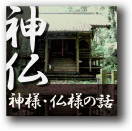
![]()


むかし むかしの 話じゃ。
「助けて、助けて。」
ある夜、母神様は子どもの声を聞いた。なにごとかと人の世におりてくると、夫婦が子どもを捨てようとしていた。
「なんと、子を捨てるのか。」
母神様は、あまりの行いにおに神のすがたになっていた。

「ひいっ。」
夫婦は、おそるおそるふりむいた。
「おっおにじゃ。」
ふうふは、大声をあげて逃げていった。
「おにじゃ、おにじゃ。」
「こどもが おににさらわれたあ。」
「おにが、わしの子を食ろうたあ。」
夫婦は 自分たちの行いをおに神様になすりつけた。
「あわれな人間め。」
おに神様は、捨てられた子をだきかかえたが、もう助かりそうになかった。そのうえ、足をしばられていた。
「家へもどらんように、しばったか。」
暗やみに目ががなれてくると、ほかにもたおれている子がいた。
ひとりは、くちいっぱいに どろを ほうばっていた。
「ひもじいて、どろをくうたか。」
ひとりは、背中に矢がささっていた。
「つらいめに合わせたな。」
おにがみさまは、静かに祈った。
「子どもたちよ、立ちなさい。」
すると、ふしぎなことに 子どもたちは 立ちあがった。
「わが家に帰ろう。」
おに神様は、きずついた子を 人の世からつれさった。
これは、夢の話か、本当の話か。ふうっと あたりが明るくなると、おすがたは母神様にもどられていた。 子宝さんと きずついた子の看病をしていた。
「母神様、この子はずっとふるえているぞ。」
「元気になれるか。」
「ああ、子宝さんにもどるのじゃ。よう めんどうをみてやれ。」
その時、また人の世から母神様を呼ぶ声がした。
「母神様、どうか子をさずけてください。与助さんもばあちゃんも笑いもしねえ。暮らしは楽ではねえが、子がいれば、もっと明るく暮らせます。」
大多喜の西 安楽山の常徳寺から聞こえた。母神様は様子をみていた。
「庄司のたえ、願いは聞いた。これを持っていけ。」
住職は、寺いっぱいにかざられた着物の中から 一つ与えた。
「そうそう、家をぬけだして 寺までこれめえ。この着物を枕の下において毎晩願いなさい。」
たえは、何度も頭を下げて山をおりていった。
「ありがとうございます。ありがとうございます。」
母神様は、住職に言われた。
「わしは、たった今 人の世に見捨てられた子をつれかえった。人は、本当に子どもがほしいのか。」
住職は、静かに答えた。
「自分の子を見捨てる人間こそ、おにでありましょう。」
母神様は 悲しそうにつぶやいた。
「人もまたおにになるのか。」
たえは この日は どんな仕事もつらくなかった。夜になると 住職に言われたように 着物を 枕の下に置き願った。
すると、ふしぎなことに 与助さんも寝たきりのばあちゃんも同じ夢を見た。三にんは、暗やみの中にいた。すうっと明るくなると、母神様が現れた。母神様は、持っていたざくろの実を割られると、ふあふあと小さな子宝さんが現れた。
「たえ、たえ、たえ。」
子宝さんは たえに集まってきた。
「わしらは、たえの子になろうかな。」
「わしは大きくなったら、よく働くぞ。」
「おらあ、おんなの子じゃが、家の手伝いができる。」
「わしゃ、わしゃ、わしゃ、なにができるかまだわからん。」
「あはははは。」
たえは、たくさんの子宝さんにかこまれてうれしかった。ふと見るとみんなの輪に入れない子がいた。
「あの子はね、人の世に生まれても何度も母神様のところにもどってくるんだよ。」
たえは、その子をだきしめた。
「おまえは、人の世で育たなかったか。」
その様子を 与助とばあちゃんが見ていた。
「たえは、子がほしんじゃのう。」
ばあちゃんの言葉に 与助は 大きな声をだした。
「ばあちゃん。」
おどろいた子宝さんはあわてて消えていった。与助は怒った。
「たえ、わしらのように貧しいもんが どうやって子を育てるんじゃ。ばかな夢は見るな。」
夢は、そこで 終わってしまった。たえは、着物をだきしめて思った。与助さんの言うとおり 子をもつのは無理なんだろうか。たえは、毎日毎日着物に祈った。ばあちゃんも、孫がほしと思った。与助は、そんなたえとばあちゃんを見ていた。与助は、寺へ行ってみた。母神様は、鬼神のすがたで与助を待っていた。鬼神様は与助をにらんだ。
「与助、おまえも子がほしくなったか。じゃが、子をさずけても食わしていけめえ。病にでもかかったら山に捨てるか、川に流すか。与助、わしを見よ。この おにの顔は おまえの顔じゃ。おには人ぞ。おまえの中におにはいる。」
与助は、寺であったことを ばあちゃんに話した。
「おら、こわい。子をさずかっても ひもじい思いをさせるのではないか。おら、おにになってしまい山に捨ててしまうかもしれん。」
ばあちゃんは、小さくうずくまる与助の背中をだきかかえた。病にかかったらなにもしてやれねえ。
「わしも、おまえを楽して育ててきたわけではねえ。与助、おにになるな。たえがおる。わしもおる。里の者もおる。人はひとりでは親になれねえ。みんなでささえて親になるんじゃ。」
与助は、背中をさすられ、ばあちゃんの言葉が身体にしみていった。
その夜、三にんは同じ夢を見た。

「たえの願いをかなえよう。だれか、ふたりの子に生まれるか。」
母神様は、ゆるりと子宝さんをまねいた。
「生まれてえ。」
「生まれてえ。」
母神様は どの子もいとおしいと見渡されたその時、手をあげず、静かにみんなを見ている あの子を見つけられた。
「おまえは手をあげんのか。」
「わしはあちこち丈夫でねえから、生まれてから手がかかる。与助とたえに苦労をかける。」
母神様は 困ったように ほほえままれた。
「子はみな、手のかかるものじゃ。おまえは優しい子じゃ。優しさは宝。この宝では足らんかのう。」
たえは、思わずとびだし、あの子をだきしめていた。
「おまえが 生まれてこい。おらも たいした力仕事はできねえ。りっぱな智恵もねえ。大きゅうなったら、おまえができる仕事をすればいい。覚えられねば、毎日おらが教える。」
子宝さんはうれしいが、すまなそうに与助を見た。与助は ふたりをだきしめた。
「生まれてこい。生まれてこい。楽な暮らしはさせてやれねえが、みなでなかよく暮らそう。」
それから次の年の秋、与助とたえの夫婦に小さい男の子が生まれた。か細く弱々しい赤子じゃったが、だれもが、その子を見るだけで、温かく幸せな気持ちになったそうな。
おしまい
(齊藤 弥四郎 編纂)