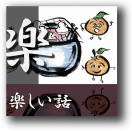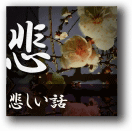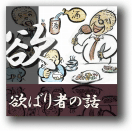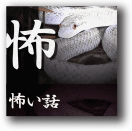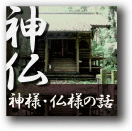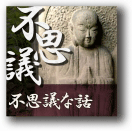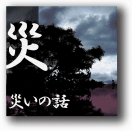1
むかし、むかし、子どもたちが、庭でクリを焼いていました。
「わあー、いいにおい。もう食べてもいいかな」
「焼けたようだ。熱いから気をつけて食べよう」

2
 そこへ、旅のとちゅうのお坊さんが通りかかりました。
そこへ、旅のとちゅうのお坊さんが通りかかりました。
お坊さんは、そんな子どもたちを見ながら、そのまま通り過ぎようとしましたが、「ぐーーーっ」と、お腹の虫が鳴いてしまいました。
それを聞いた子どもたちは、笑いながらお坊さんにいいました。
「あはははは。お坊さん、お腹が空いているのかい?」
お坊さんは、はずかしそうに頭をかきながら言いました。
「はい。じつは昨日から、何も食べていないのです」
すると子どもたちは、お坊さんに焼いたクリをさし出しました。
「これを食べなよ」
「いや、それはみんなの大事なクリでしょう」
「いいよ、まだたくさんあるから食べなよ」
「それでは、えんりょなく、いただくとするか」
こうしてお坊さんは、子どもたちに焼きグリをごちそうなりました。
3
 焼きグリを食べ終わった坊さんは、子どもたちがすてた、焼けすぎてまっ黒になった焼きグリをひろうと、それを地面にうめました。
焼きグリを食べ終わった坊さんは、子どもたちがすてた、焼けすぎてまっ黒になった焼きグリをひろうと、それを地面にうめました。
「あれ? お坊さん、焼いたクリを植えても、芽は出ないよ」
「そうかね・・・」
お坊さんはほほえむと、
「ありがとさん。おいしかったよ」
と、子どもたちにお礼を言って、また旅立ちました。
4
 さて、その次の年のです。
さて、その次の年のです。
不思議なことにお坊さんが植えた焼きグリから芽が出て、立派なクリの木へと育ったのです。
そしてさらに不思議な事に、この栗の木に出来たクリの実は、片側半分が焼けたように色が変わっていたのです。
お坊さんのことを「ごしょうにん」ともいいます。それでこのクリの木を『ごしょうにんさまの焼きグリ』とよんで村人たちは大事にしました。しかし、月日がたってやがてかれてしまい今は見ることはできません。
おしまい
(齊藤 弥四郎)