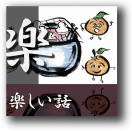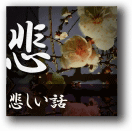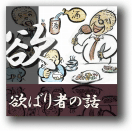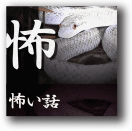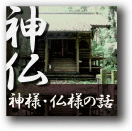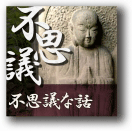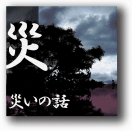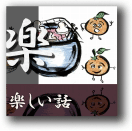



十月の暗い夜のことでした。たわわに実をつけた柿の木畑に人影がありました。ふたりの少年です。キョロキョロあたりを見まわしています。
「おれが木にのぼって、枝をゆすって柿を落とすから、おまえは、下でひろえ」
「ああ、わかった。柿の木は折れやすいから気をつけてのぼれよ」
「あいよ」
小柄な少年が木にのぼり、手をのばしてゆすりました。ポトポト、柿が落ちてきます。
下で柿をひろう少年は、大あわて。頭には落ちてくるし、あっちにもこっちにもポトポト落ちてきます。背負ってきた竹かごをおろしてひろい始めました。
「いっこ、にこ、さんこ・・・じゅっこ、じゅういっこ・・・」
と、最初は数えていましたが、途中からは数えることもわすれ、あっちに行ったりこっちに行ったり大あわて。
そのうちに、柿をひろっていた少年が
「おーい、落ちた落ちた・・・」
と、とつぜん叫びました。柿の木の上にいる少年は
「ああ、落ちるはずだよ。おれが落としているからさ」
「いやいや、落ちた落ちた・・・」
前よりも大きな声でさけびます。
「声が大きすぎるぞ」
「いやいや、落ちたんだ・・・」
「落ちるのはあたりまえだ。つべこべ
言ってねえで、早くひろえ」
「ちがう、ちがう。ドブに落ちたんだ」
すると、木の上の男は、
「それはドブか? そこにあるのは肥(こえ)だめだ。肥だめに落ちたのは、きたないから、すてろ」
「くせー」
「臭いのは腐った柿だ。腐った柿は食えねえから、すてろ」
「いやいや、落ちたんだ。落ちたんだ」
「落ちた落ちたと何度も言うな。わかったから」
「肥だめに落ちたのは柿でねー。おれだ」
暗い夜の柿の木畑に少年の声が響きます。
やがて提灯をつけて集まってきた大人達に大目玉をくらったとさ。
おしまい
(齊藤 弥四郎 著)