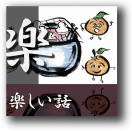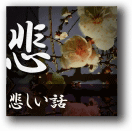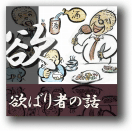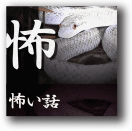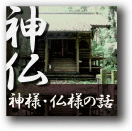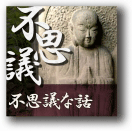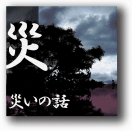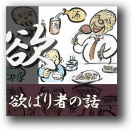



むかし、勝浦は市野川の山の中に、ふながたくさんいる小さな沼がありました。
秋の刈り人れも終わって、白いすすきの穂が秋風にゆれるある日のことでした。
一人の農夫が沼への道を、竹のビグを腰につけ、手につりざおを持って上っていきました。沼に着いた農夫は、汗びっしょりで休む間もなく、すぐに釣りのしかけをつくって、沼につり糸を投げいれました。しばらくすると、ビクッと手ごたえがあり、いそいでひき上げると、水の中で白いものが勢いよく右に左に動きました。気合を人れて引きぬくと、水面をパシヤバシヤたたいて、ふなが釣れました。農夫は、息をフーッとついて、
「これ、これ、この感じだ」
と、ひとりごとをいいながら、ふな釣りを楽しんでいました。
この日は、釣れて釣れて昼ごろには、ふなが竹のビグいっぱいになりました。農夫は、釣りが楽しくてたまらずに、もっともっととつりつづけました。とうとう夕焼け空が広がったので、ビクにはいらないふなは木の枝にさし、肩にかついで帰りました。
農夫は家に着くと、家族に、
「すごいぞ、こんなに大漁だぞ」
と、叫びました。そして、家から出てきた家族に、
「ほら、見てみろ」
と肩から、ふなをさした木の枝をおろしました。
すると、木の枝には、ふなではなく、紅葉し始めた木の葉があるだけでした。あわてた農夫は、ビクの中をあけてみました。しかし、そこにも、ふなのかわりに赤や黄の木の葉はかいっているばかりでした。ふなが木の葉に変わってしまったのは、農夫があまりに欲ばったからだといわれています。
おしまい
(齊藤 弥四郎 著)