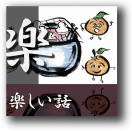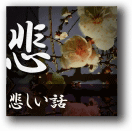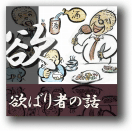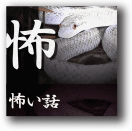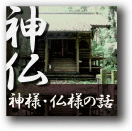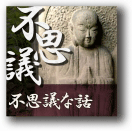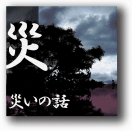![]()



夷隅町、増田と行川(なめかわ)の境に小さな川が流れている。この川近くに「夜泣き地蔵」と呼ばれる小さな祠(ほこら)がまつられている。この祠には次のような話が伝えられている。
むかしむかしのことだ。京の都の戦さで負け、この地まで落ちのびてきた夫婦がいた。身分の高い人らしく、錦の着物を身につけていたが、長い逃亡生活に錦の着物も、汗と泥にまみれていた。夫の顔は無精ひげにおおわれ、左足に傷を負い、足を引きずっている。妻は頬(ほほ)がこけ、よごれた長い髪は風に乱れ、乳飲み子を抱いていた。
「もう一歩も前に進むことができません」
「なにを申す。都からこの辺境まで逃げ延びてきたではないか」
「……この3日間、満足に食べ物さえ口にしていません。赤ん坊もおなかをすかせて泣いてばかりいます」
「……………」
妻の言葉に夫はだまってしまった。あたたかな春の風に小鳥の声がきこえてきた。2人はだまったままだった。
妻が青空に映えた桜の花を見ながら、口を開いた。
「都も桜の季節でしょうねぇ」
「ああ、都の桜も咲くころだね」
「……都の生活……楽しかったです」
「ああ、楽しかったね。おまえと過ごした都での生活、今は夢のようだ」
「あなたと初めてお会いしたのは、ちょうど、このような春でしたね。……新録におおわれ、桜がさき、小鳥が鳴き……」
「わしも、君に初めて会ったのを、きのうのことのように思い出すよ」
「まあ、うれしい。あの日のことおぼえていらっしゃいますか………」
「若菜をつむ君の姿、美しく可愛かったねぇ。わしはその日以来、君のことが頭からはなれなくなったのじゃ」
「私こそ、あなたさまの凛々(りり)しいお姿を目にしたあの日は、眠れませんでした」
「ははは……そうだったのか、うれしいことを言ってくれるのぅ」
二人は遠い都での生活を思い出し、しばし疲れを忘れていた。都の話ははずんだ。はじめて二人が出会った桜の春、水遊びをした夏、紅葉狩りの秋、嵐山の雪……。
二人の顔はうっとりとしておだやかであった。
………………
……時が流れた。
「都に帰りましょう」
「都に?」
「そう、都にです」
「……敵が……」
「敵」という言葉に現実にもどされ、顔はけわしくなった。
また沈黙がつづき、小鳥の声と川音と春風があたりを支配した。
………………
妻が口を開いた
「都に帰りましょう」
「帰ろうか………」
「……このまま死んだら、魂になって都に帰れるでしょうか………それも二人が出会ったあの都に………」
「二人が出会ったあの時代に……….」
「楽しかったあのころに………」
………………
二人の声は涙声にかわっていた。
「帰りたい。もう一度帰りたい、都に……あなたと出会ったあのころに……」
突然、妻が泣き叫んだ。夫は妻を抱いた。二人は泣き続けた。
やがて、赤ん坊の泣き声で、二人はわれに返った。
「この子をどうしましょう」
「二人のために赤ん坊の命をうばうことは………..」
「どうすればいいんです」
「……………」
「三人一緒に死んだほうが幸せです」
「いや、この子にも生きる権利がある………この子は生かしてやりたい」
「………そうですね。このような桜の美しさも、この子はまだ目にしたことがなく、私たちのような恋も知らないのです。この子の人生はこれから……」
「……………」
「この橋のたもとに置いておけば、通りがかりの人がひろって……育ててくれるのでは………」
妻は着物をぬいで赤ん坊をつつんだ。そうして胸から紅(あか)いお守り袋を取り出すと、赤ん坊のふところに入れ、赤ん坊を草むらの上にそっと置いた。
二人は、手をとりあって、近くの川に入って行った。
桜の花が、はらはら散った。
その後、残された赤ん坊は、大多喜城下に向かっていた旅人に発見されたが、やせおとろえて亡くなっていた。
不思議なことがおこったのは、その後だ。日暮れに、この橋を通ると赤ん坊の泣き声が聞こえてくるという。野良仕事を終えてかえってくるお百姓さん。今夜の宿を求めて足早に急ぐ旅人が哀(かな)しげに泣く赤ん坊の声を聞いたといううわさがひろまった。
「あの泣き声は捨てられた赤ん坊のなげきだろう」
「ほんとうにかわいそうに」 ……とあわれんだ。
「赤ん坊を弔(とむら)ってやろう」
ということになり、橋のたもとに小さな祠(ほこら)を建てて、冥福(めいふく)を祈った。それ以来、泣き声は聞こえなくなった。その後もここを通る人たちは赤ん坊の冥福を祈った。
「赤ん坊があの世に行くには、三途の川という河原を渡らなければならないという。その時、小石を積み上げながら渡るという。しかし鬼がじゃまをして小石の山を崩していく。そこで、現世の人が小石を積んで、赤ん坊を助けようとする」
という言い伝えがある。それで祠のそばには小石が積み上げられた。
やがて、野良仕事で疲れて帰って夕食のしたくをし、夜なべ仕事をする農家の女たちが夜中に赤ん坊が泣いた時に
「赤ん坊よ、野良仕事で疲れているんだ。せめて泣かないでおくれ」
という願いから、祠のお参りをするようになったという。この祠をおがむと不思議なことに、火のついたように泣いていた赤ん坊も泣き止んだという。今も祠は「夜泣き地蔵」とよばれ、道ばたに祭られている。
おしまい
(齊藤 弥四郎 著)